| 水道管の中のオルフェウス 登場人物に関するメモ |
 |
1
ある男、年齢30過ぎ、元ボクサー。名前は重要ではないが、身体は、まだボクシングを続けるのに十分な能力を備えている。
彼は引退する。その理由。
彼は考える。自分が世界の頂点に立ったのは、各国の数ある格闘技の中の一部の、それも偶然を含んだ舜間ではなかったか。世界チャンピオンといっても、自分のクラスではヘビー級の4回戦にも勝てるかどうか。チャンピオンになるのがどれほど大変な事か、それは十分自覚している。そこに大きな意味があることも理解している。だが、それはリングの上での話である。
競技場を離れた時のボクサーの強さとは何なのか。具体的強さの事ではない。それは自分の肉体に聞けばはっきりわかる。ここでいう強さは、概念のことである。誰も観る人間がいない場所でボクサーは、ルールに則して試合ができるのか。誰も関心を示さなくても、人間は9秒台前半を目指して100mを走るのか。
この都市化された社会で、たまに野蛮といわれるこの肉体にアリバイを与えてやりたい。
|
 |
2
ある女。男にとって名前が重要でないと同じように女にとっては年令も大したことではない。
彼女は、今、ここ(東京)にいるが、住んでいるのかどうかはわからない。彼女が生まれたのは、東京以外のところである。もしかしたら日本でもないのかも知れない。
彼女は、故郷ということばに違和感を持つ。自分がある時間、ある場所に生まれたのは、自分にとって偶然ではないのか。彼女は、いろいろな国をまわり、自分の想像の内に故郷を育ててゆく。その各々の国の文化が、彼女の心の故郷にどのような影響を与えたかはわからない。
どこかの国のある場所、彼女は大きな木の下に身体を横たえていた。そこに突然スコールがやってきた。
全てを洗い流しそうな勢いだ。上を見上げると顔が痛い。遠くの街も雨にけむって見えない。
女はなつかしい風景だと思う。子供の頃、溺れそうになった時、海の中から空が見えたのを覚えている。それとも、もっと昔の景色かも知れない。その時、彼女を形づくっていた、様々のもの過去とか、言葉とか文化とか、そういったものが全て流れおとされ解放された気分になった。
自然と身体が動き始め、踊りだす。
|
 |
3
男の物語風スケッチ
俺は今まで戦いつづけてきた。誰もそれを嗤う(わらう)ことは出来ない。
チャンピオンにもなり、頂点も経験した。皆が俺を見つめていた。そのまなざしから受ける快感は例えようがない。俺は皆の夢を背負っているのだ。俺が彼等の夢なのだ。本当にそうなのか?一舜浮かぶこの疑惑を、目も眩むような喝采がかき消す。
しかし、誰もいなくなって暗い部屋で、ひとりになった時、再び疑惑がよみがえる。あの時の自分と、今の自分は同じ人間なのだろうか。自分に対して疑惑を持ったのは初めてだ。俺はこのとき初めて深い孤独を感じた。テレビに映っている俺は、俺なのだろうか。
この俺の身体からボクシングという役割を取り去った時、このきたえ上げられた肉体は、一体何になるのか。
俺が試合を続けてきたのは、高揚感に魅せられたからだ。あの何とも言えない高鳴りを与えてくれたのは、客ではない。それは対戦相手だ。奴等は俺を俺以上のものに高めてくれ、俺というものを自覚させてくれた。リアリティというものをそこに感じた。
だが、テレビという映像はそれを写し出さない。小じんまりとしたフレームの中には戦いは矮小化された見せ物となり、肉体は破壊性を失い健康体の見本となり下がっている。
かつて戦いには尊厳があり、見せ物にはキケンと恐怖をあわせもち、肉体は偉大ではなかったか。
俺は、俺と俺を見ている奴の間にあるフレームを取り除きたい。
もっとも、虚構化という言葉を使えば、それは避けられないだろうな。意識しはじめると、すでに虚構が始まるわけだから、そういえば、シュールレアリズムという言葉があったっけ。
|
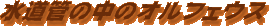 |
暗闇
場所は、どこかの海岸だが、時代も時刻も定かではない。暗闇の中から波の音だけが聞こえてくる。
寄せは返す波の音。太古の昔から未来へ無限に繰り返されるかのようだ。
浜辺にかすかに光がさす。黒い海が波打っている。砂浜に、黒く四角い物体が打ち上げられている。
ある都市の高層ビルからの眺望、東京 現代
遠くに水平線が見える。
海と空との境目がかすんでいてはっきり見えない。その間をいきなり建築物が、空を突き破るように高くいくつも飛び出している。陸地は建造物に被われて見えない。波の音もここまでは届かず、都会の喧噪が神経をいらだたせる。
| *補足) |
こういう都市の眺望は、私にある光景を思い出させる。
万里の長城を扱った、10年位前のTVドキュメントだったと思う。長城の果てはどこまで続いているのか、というのが目的のひとつだったが、カメラに写し出されたのは砂に被われた石の壁だった。あの隆盛を誇った秦大国の偉大な壁は、ゴビ砂漠の下に飲み込まれ消え去っていた。
水がアジアやアメリカの都市を破壊したのは記憶に新しい。都市が大地を侵蝕しつくしそうな勢いだが、土と水を、人間は虚構化しつくすことはできないだろう。
自然破壊という言葉があるが、人間に自然を破壊することなどできない。人間に適応する環境を破壊するだけだ。そのあとに表れるのも自然である。ただ人間が住むのに適さないだけである。
|
|
 |
渋谷駅、その全体と周辺
JR、銀座線、東急東横線、半蔵門線・・・、様々な路線がこの駅に乗り入れている。同じように多くの幹線道路もここで交わっている。おびただしい数の人間が、ここに集まり散ってゆく。
ある方面にゆくと、宇田川町という地名を見つけることができる。しかし、もはや川は流れていない。人間が、川の町を流れてゆくだけだ。
渋谷駅 南口、渋谷川
南口から宮益坂の方を見ると、大きなビルや道路が目に入る。都市の流れを作っているのがわかる。右手には大きな歩道橋が架かっている。こちらに流れてゆく人々も多い。その歩道橋の下に、本物の橋がある。人々は橋と意識しないで渡っているようだが、その”稲荷橋”という橋の下を渋谷川が流れている。
参道橋付近
歩道橋の上から、道路を往来する車の流れを見下ろす男Aがいる。
Aの視線は、道路からその脇にある、警察の派出所へ移る。睨むような目つきである。
Aは歩道橋を降りて参道橋に立つ。
“渋谷川はここで姿を消す”という意味の事が書かれてある看板を見る。
| A) |
「川もないのに何故橋を残す?贖罪か?感傷か?とにかく、自然がここで消えるのだ。今の俺には、ふさわしい場所かも知れない。ここを俺の出発点としよう。」 |
| *補足) |
男は、日常的な生活習慣に価値基準を置いてきた。しかし、自分が他人に見られるという虚構の対象になった時、自分が身を落ち着けている世界が、単に約束事でつくられた閉じた世界に過ぎないのではないかいう考えになってきていた。
何かが自分の中から失われた。そういう疎外感を覚え始めた。
|
|
 |
路上
ホームレス風の男が、大きな紙袋をかかえて歩いてくる。
Aは不用意にその男にぶつかり、袋の中に入っていたたくさんのオレンジが落ちて、はじけるように飛び散って転がってゆく。
Aはその中のひとつを拾おうとする。
その時、バイクの音がする。Aはその方向へ顔を向ける。彼の目に、オレンジと同じ大きさのバイクのヘッドライトが写る。バイクはAの前を通り過ぎて、明治神宮の方へ去ってゆく。
| A) |
神社の杜の方を見る。彼の耳に音が聞こえる。風の音か、動物の鳴き声か、海鳴りか。 |
明治神宮原宿口の入口
Aは聳え立つ鳥居からガードマンの方へと視線を向ける。
| A) |
「おまえたちは、何から何を護っている」 |
| A) |
杜の道を中へと入ってゆく。 |
整備された道、近代的な建物、清酒会社の広告かと思わせるような酒の銘柄の羅列。杜のすぐ横を車が走り、高架線の上を電車が走る音が聞こえる。
| A) |
杜の木々を見上げ訴えかけるように言う。
「全ての秩序を呑み込むような、恐ろしいまでの神秘と威厳はどこに失ってきた。」 |
かすかな鳴き声のような音が、車と線路の騒音にかき消される。
|
 |
神宮橋
| A) |
憔悴しきった表情で原宿駅の方へゆく。
橋の上から山手線が原宿駅の方に来る。 |
| A) |
じっと見つめている。 |
Aが見ているのは電車ではなくて線路のようだ。
どこまで行っても、とても交わりそうにない平行に走っている線路が鈍く光っている。
原宿駅、ホーム
電車が入ってきて、人々が吐き出されるように出てくる。
入れ替わりに待っていた人々が乗り込んで、電車は発車する。
別の電車が入ってくる。
| A) |
何か期待するように、その様子を見つめ、何台目かを見送る。人々はAの存在にすら気づかないようだ。 |
| A) |
入ってくる電車に近づく。窓ガラスに写った自分の姿が、中にいる人の姿と重なってしまう。体は自分の姿だが、首から上は人の顔になっている。 |
| A) |
ショックを受けたような顔。 |
| A) |
慌てて周囲を見回す。誰か自分を見つめている者はいないか。俺を求めている奴はいないのか。 |
| A) |
神経を集中させるが、やがて力なく歩き出す。 |
海辺
浜辺を自転車を押して歩く男、荷台には旅行カバンがくくりつけてある。
|
 |
路上、参道橋から渋谷に通じる路。
| A) |
身を横たえて耳を道路にくっつけている。この道路の下を川が流れているかどうか、音を確かめようとしているようだ。 |
| A) |
周囲を見渡す。昔からある人家が遠くにあり、近代的にデザインされた店舗が道路に面して軒を並べ、その前を人が往来している。のどかで幸福そうな表情である。 |
| A) |
「俺は何をしている。川がなくても誰も不幸になるわけじゃない。」
昔からの木をそのまま残してある場所、新しく店舗を建てるための建設現場、怪物が見下ろしているような印象の高い建物。それらのものがAの目に入ってくる。 |
| A) |
もう一度散歩する人々を振り返る。
「誰も不幸になるわけじゃない・・・。」 |
路上
遠くをバイクが疾走する。
病人のようなホームレスが歩いてゆく。
宮益公園につながる歩道橋の上
Aは病人のようなホームレスを目で追っている。
高架になっている山手線の下を平行して道路が走っている。その路肩にホームレスの住居が並んでいる。その側を先程のホームレスが歩いてゆく。Aは彼が気になるらしく、追いかけてゆく。
|
 |
宮益公園
ホームレス達が集まって酒盛を開いている。その中に病気風の男も混ざっている。
しかし、よく見ると、ホームレスだけの集団ではないようで、異様な風体をした連中もいる。数としたら、彼等の方が多いようだ。
Aもその中に入る。誰も何も言わない。自然にとけ込む。Aに安らぎの表情が浮かぶ。
| A) |
「川のにおいがしたような気がしたんだが。」 |
| △) |
「そうか」 |
| A) |
「あの道路の下を川が流れているのを知っているか」 |
| △) |
「そうか」 |
| A) |
「ここで何をしている?」 |
| △) |
「酒を飲んでいる。」 |
| A) |
(力を落として)「そうか。」 |
| A) |
立ち去ろうとする。 |
| △) |
「週末に来ないか」 |
| A) |
(期待して)「何かあるのか?」 |
| △) |
「ケイバだ」 |
| A) |
「そうか」 |
| A) |
立ち去る |
Aの背に嘲笑がひびく。
|
 |
渋谷駅南口方面、宮益坂交差点付近
Aの周囲をたくさんの車が行き交う。車が信号で止まると、おびただしい数の人々がAの側を通り過ぎていく。都会の海に溺れているようだ。
Aは逃れるように、宮益坂を這い上がる。
そして、昔は富士山が見えたという方向を見る。が、大きなビルがさえぎって見えない。
海辺 時間は不明、だが周辺は暗い。
風景は墨絵のようにシルエット状にうつっている。
波の音が聞こえる浜辺に、四角い物が見える。旅行カバンのようだ。
いつの間に現れたのか、女がカバンの方に近づく。波の音に、時計の時を刻む音がかぶさる。
女はカバンを開ける。本、新聞、楽譜、カメラ、映写機、パソコン、時計、女はカバンの周囲に12本のローソクを立て、火をつける。
そして、時計を切り刻み燃やしてしまう。炎は勢いを以って燃え上がる。燃え尽きた後には、深く、暗い穴が口を開けている。女は踊るように周囲を回る。
| *補足) |
無限を一舜に凝縮し、永遠という観念にしてしまう装置。それを、イマジネーションを生み出す源点として思想化する。スタンリー・キューブリックの『2001:スペースオデッセイ』のテーマの一部だが、ここではオデッセウスより、帰る場所もあるかどうかわからないオルフェウスの方が適当だろう。 |
渋谷
波の音は相変わらず小刻みにくり返している。
その音をかき消すような、ジェット機の音がおそう。ジェット機の音がする空の下に渋谷の街がある。
|
 |
渋谷南口
多勢の人が列をなして歩いてゆく。様々な表情だが、豊かである。人の相も色々である。
ウィンズ付近
屋台はたくさんの人でにぎわっている。
ウィンズの中、オッズを見る者、予想する者、金を出す者、レースに集中している顔、興奮している顔、落胆している顔、怒っている顔、それらの雰囲気は、公園で酒盛りをしていた連中のそれと似ている。よく見ると彼等も来ている。
|
 |
渋谷南口、歩道橋
| A) |
歩道橋から人々の列を見下ろしている。
ホームレス風の男が、Aの横に来て馬券を見せる。 |
<画面はレース>
| A) |
わずか数分の、筋書きのないドラマというわけか。
自分の思想を、馬を選んでイメージし、馬券を買うことによってそれを具体化するわけだな。
勝てば、想いが金になって還ってくる。
金で買える夢か。
ふざけるな!
自分は安全なところにいて、何が夢だ。何が思想だ。馬の本能はどうなる。馬に想いをはせたことはあるか。 |
<<ここからAの独白>>
<Aの歴戦の映像にかぶってAの独白が続く。>
リングの上では、俺はもっと疾く走ったよ。試合の苦しさは、あんたに言ってもしょうがないし、話す気もないが、走る苦しさは誰かに話してみたいと思っていた。
最初は、まわりの奴等を皆敵だと思ったよ。どいつもこいつもブッ飛ばしてやる。実際、そうして勝ってきた。若さも勢いもあった。
必死にやってきて気づいてみると、周囲には見覚えのある顔だけになっていた。皆強かった。そんな中から、たまたま俺が頭ひとつ勝ち抜けた。俺は走り始めた。
挑戦してくる奴が、後を絶たなかった。俺は抜かれるわけにはいかなかった。でも、その頃はまだ走るための道があった。追いついてくる奴らをねじ伏せて、俺はトップに立った。挑戦者は、いつも強い奴だった。このあたりから、俺は走っているんじゃない、逃げているんだと感じだした。敵は跡切れる事なく続く。無限に続くように思えた。
死ぬまで続くんだろうなと考えた。それでも、足を止めるわけにはいかない。捕まると本当に死ぬような気がしてた。死を意識し始めてから、自分が、どこに向かって走っているのかわからなくなってきた。目の前に黒い大きな穴が見えた。そして、自分がどこにいるのか見えなくなってきた。ただ、足はこびだけが規則的にくりかえされている。空中を走っているような感じだ。
何だ、この虚無感はと思っていた。
そんな俺の感覚に触れたのが、あんたたちだったんだが・・・。
| A) |
「何だこの体たらくは、(ホームレスの馬券を振り上げる)おまえたちは馬にすら乗れないじゃないか。」 |
| 男) |
「馬はどこを走ればいいんだ?」 |
|
 |
| A) |
「野生の本能にまかせればいい」 |
| 男) |
「馬が走る姿を美しいとは思わないか」 |
| A) |
「馬には関係ないことだ」 |
| 男) |
「どういう風に考えても、人間が勝手に考えているにすぎない。自然といっても俺たちが思い描いているだけだろう。馬の方から意識して関わってこれるわけではないだろう。」 |
| A) |
「あの川を見てみろ、(渋谷川を指す)あれが川と言えるのか。この川が生きているといえるのか」 |
| A) |
男の方を振りかえると、男はコートを身につけ、炎のともったローソクをたずさえている。そして渋谷川をさす。 |
| A) |
その方向を見ると、かなた向こうに架かった橋の上に浜辺に現れた女が、立っているのを見つける。
男の方に向き直り、何か問いたそう顔をするが、そこには誰もいない。が、別の男が別の場所で、同じ格好でローソクを持っている姿を見つける。
再び川の方を見ると、一つ手前の橋の上に、同じ女が立っている。ローソクを持った男たちの人数も増えて、人混みの中にあちこちといる。女は、もっと近くの橋の上に立ってこちらを見ている。
男たちの持ったローソクの光が、あるひとつの場所へ集まってゆく。 |
| A) |
川の方を見るが、もう女はいない。
ローソクは、駅南口へとつながる地下道の入り口に集まったようだが、男たちの姿は消えてローソクだけがそこで燃えつづけている。入り口は大きなホラ穴のようだ。
Aはひきづられるように、ひとりでその中に入ってゆく。Aの耳に川の流れる音が聞こえる。 |
|
 |
日本文学館、洋館
黄昏の光の中に佇む洋館。
その前にAが立ちすくんでいる。暮れかかる太陽の光がAの顔に陰影をつけ、思慮深さを強調している。黄金色の光をうけた、洋館の周りの林の中から、ローソクを持った男たちが、ゆっくりと歩み出る。ひとり、ふたり・・・、そしてAの周りを取り囲むように12人現れる。その男たちの輪の外から、女が立出る。
女は空を見上がる、 Aも同じように空を見上げる。一舜空が回転したようだ。
女はAから離れる、だが視線はAから離れない。Aも凍りついたように女を見つめている。全てが止まったままのように思える。時がどのくらいたったかわからない。
突然、華麗に女が動き始める。奔放な動き、そしてそれは、なめらかな形となり、流れとなってAの体を突き刺す。Aに試合の昂揚感がよみがえる。
あれは、いつだたっだろう。
俺より、はるかに強い奴と戦った。
思ってもみないところからパンチが飛んできたし、信じられない距離から伸びてきた。
俺がどう戦ったかは覚えていない。
気がつくと俺の手が上げられていた。
試合が終わっあと、自分が変わったような気がした。
変化という言葉を意識した。
今それを思い出した。
女のめくるめく踊りにAは一体感を覚える。
俺たちが世界の周りを回っているのか、世界が俺たちの周りを回っているのか。
無限が一舜に凝縮する時だ。
空白の時間、洋館の前には、やはり同じようにAがひとりで佇んでいる。もう周囲には誰もいない静寂があたりを包んでいる。
最初と同じ構図だが、Aの足元に大きな絵の額縁が置いてある。
Aは取り上げて、それを通して洋館を見る。美しい絵のようだ。
しかし反対から見れば、Aも額縁の中で一片の絵の構図の一部を構成しているのがわかる。
Aは、それを置いて歩き去る。門を出ると、ここは都会にあるミュージアムの一つだということが示されている。
|
 |
道路には車が走り、歩道をコンビニの袋を下げたオバちゃんが歩いている。
Aのそばをどこかで見た顔の男が、競馬新聞を片手にあいさつしてゆく。
Aも彼の方に笑顔を送り歩き去ってゆく。
俺の後ろに言葉はできる、
俺の後ろに形ができる、
俺の後ろに道はできる、
そしていつも歴史は誰かにつくられる。
だが
俺は言葉を信じない
事実も真実も俺のパンチの速さにはついてこれない。
俺の歴史はまだこの身体の中にある。
まだ誰も見たことがない。
<end>
|



